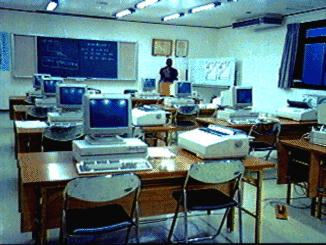電子計算機の歴史(下)
ここでは、コンピュータのミニ歴史をお話しします。
1980年代に入り半導体技術は飛躍的に発達しました。
論理演算回路もICやLSIで構成されるようになりました。
それまでは、トランジスタやダイオードで構成されていました。
メモリーもコアメモリからICメモリとなり容量も飛躍的に増えました。
とはいえ、256KBから512KB
DASD(ディスク)容量は、140MBから460MB程度と増えました。
なによりも、ディスプレイ端末からのオンラインエントリーが出来るようになったこと。
ここで紹介するのは富士通のオフコン今のKシリーズの前にあったシリーズ
VシリーズのうちV830とV850です。
 FACOM V830 構成説明
FACOM V830 構成説明
80桁x24行 グリーンキャラクタディスプレイ
漢字は使えません。これが標準的な端末でした。
OSは、UNIOS F/4という富士通独自のOSです。
UNIXを除いて各社ともほとんどが独自OSでした。
このOSの性能が各社のコンピュータの差と言っても過言ではありませんでした。
この時代からマイクロコンピュータの技術が発達し出しました。
1985年富士通の新型はFACOM V850
 FACOM V850 機器構成
FACOM V850 機器構成
ディスク容量は460MB
専用回線2回線(4800BPS)
公衆回線1回線(2400BPS)
仮名文字タイプのラインプリンター
エントリー端末10台


正面左に写っているのがK230S
正面右に写っているのはデータライターと言ってオフラインで紙テープにデータを穿孔する装置です。
右側に写っているのがF2770
1989年 汎用機の世界では

富士通 M730汎用コンピュータ
OSは、ESP−3と言う富士通独自のOS
日本語ラインプリンター(NLP)
カラーディスプレイによる日本語端末
端末機にFACOM G150
キャドシステムと事務処理の並行処理(2CPU)
ディスク容量は2.6GB
専用回線3回線
公衆回線2回線
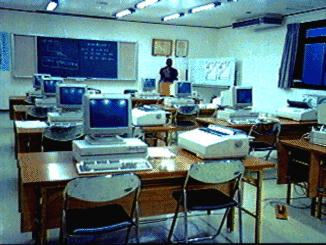
ワークステーションFACOM G150
(現在FM−G1500 K1500α)
1989年当時 UNIXベースのOS
SX−Gは、既にマルチウィンドウによる処理を実現
プルダウンメニュー・システムブラウザ機能あり
CPUは、MC68020 メモリー4MB
ディスク130MBの性能でした。
時は流れホストマシンもGS8300に端末はパソコンとなり、サーバーが入り今までの使い方は大きく変わりました。
事務所のOA化が言われ出しワープロも普及しはじめました。

電子計算機の歴史(上)へ
マイコンの歴史へ
 FACOM V830 構成説明
FACOM V830 構成説明
 FACOM V850 機器構成
FACOM V850 機器構成