電子計算機の歴史(上)
ようこそお越し下さいました。
ここでは、コンピュータのミニ歴史をお話しします。
私が初めてコンピュータを使ったのは1970年。日本万国博覧会の年でした。
機種は、日本電気のNEAC2200−50と言う機種でした。
当時日本のコンピュータは、他に富士通のFACOM230シリーズ
日立のHITAC。沖電気のOKITAC。東芝のTOSBAC。
三菱電機のMELCOM。
外国製では、IBM、ユニバックなど、また、沖電気と合弁で沖ユニバックOUKなど。
ちなみに、当時のNECのコンピュータはキャラクタマシンといって、1文字を6ピットで
表現していました。データやプログラムの入力は紙テープといってリボン状の紙のテープに
孔をあけ光を通す通さないでデータを読みとりました。
なお、当時すでにコボル言語を使用していました。
私が会社にはいって使ったコンピュータは富士通製のFACOM230−10でした。
 FACOM230−10構成説明
FACOM230−10構成説明
右側より、ファコムライター
文字は、英数字とカナ特殊記号の活字による印刷
本体、8ビットCPUに
メモリー8KB
内蔵64KB磁気ドラム
注意・単位は間違っておりません
PTR 紙テープリーダ
PTP 紙テープパンチ
LP ラインプリンター
プログラム開発には、カナコボル
その他、アトム、ウランなど?!
*カナコボルについて
イ. COMPUTE コタエ ニ スウ1 ナ スウ2.
ロ. COMPUTE KOTAE = SUU1 + SUU2.
ハ. LET KOTAE = SUU1 + SUU2
イ.がカナコボル ロ.が通常のコボル ハ.はベーシック
1974年富士通の新型はFACOM230−15
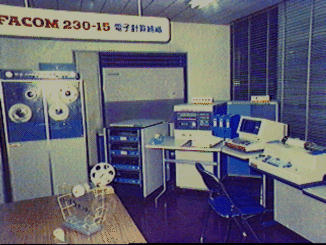 FACOM230−15機器構成
FACOM230−15機器構成
コンソールタイプライター
又は、キャラクタディスプレイ
本体、16ビットCPU
16KBメモリー、131KB磁気ドラム
可変型2.45MBディスク
2ドライブ
PTP、PTR
ラインプリンター
MTユニット
なお、メモリーは会社の実装値です。
OSとして、スパイラルという独自のOSがつきました。
このクラスの機種では、バッチ処理(データの一括処理)が一般的でした。
この写真は当時大阪市北区堂島にあった富士通ショウルームでの写真です
ネットワークを組む方法としてテレックスを利用しました
 送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し
送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し
それをバッチ処理していました。
バッチ処理からオンラインリアルタイム処理へ
1980年代に入りコンピュータの使い方は、大企業だけであったオンライン処理が
小型のコンピュータでも実現するようになってきた。
電子計算機の歴史(下)へ
マイコンの歴史へ
 FACOM230−10構成説明
FACOM230−10構成説明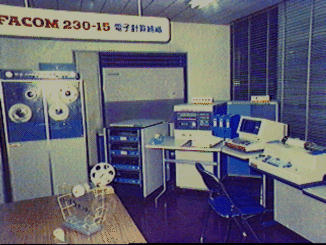 FACOM230−15機器構成
FACOM230−15機器構成 送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し
送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し